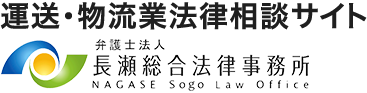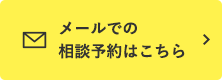2026/01/20 コラム
交通事故における会社の「使用者責任」とは?問われるケース・免責・損害賠償を弁護士が解説
はじめに
運送業を営む企業にとって、交通事故は避けて通れない重大な経営リスクです。どれほど安全教育を徹底していても、従業員が業務中に事故を起こしてしまう可能性を完全にゼロにすることは困難だからです。
従業員が交通事故を起こした場合、実際にハンドルを握っていた運転手本人が法的責任を負うことはもちろんですが、会社もまた、被害者に対して損害賠償責任を負うことになります。これを民法上の「使用者責任」といいます。
「なぜ会社が責任を負わなければならないのか」「会社が責任を免れるケースはないのか」「事故を起こした従業員に損害額を請求できるのか」といった疑問は、多くの経営者様が抱かれる悩みでしょう。特に運送業においては、車両の使用頻度や走行距離が他業種と比較して圧倒的に多く、事故の規模も大きくなりがちであるため、使用者責任の範囲と対策を正確に理解しておくことは、企業の存続に関わる重要事項といえます。
本稿では、運送業における交通事故と会社の使用者責任について、その成立要件から「事業の執行」の範囲、免責の可能性、そして従業員への求償権(損害賠償の負担)に至るまで解説します。
運送業の交通事故に関するQ&A
Q1. 従業員が配送中に事故を起こしました。会社は必ず責任を負わなければなりませんか?
原則として、会社は被害者に対して損害賠償責任を負います。
民法715条の「使用者責任」に基づき、従業員が業務の執行について第三者に損害を与えた場合、使用者である会社も連帯して賠償責任を負うことが定められています。また、人身事故の場合は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく「運行供用者責任」も問われることになり、会社が責任を免れることは困難です。
Q2. 従業員が会社のトラックを無断で私用に使って事故を起こした場合でも、会社は責任を負いますか?
多くのケースで責任を負う可能性があります。
「業務の執行」の範囲は、実際に業務中であったかどうかだけでなく、外形上(見た目上)業務の範囲内と見られるかどうか(外形標準説)によって判断されます。会社のロゴが入ったトラックを使用している場合や、鍵の管理状況などによっては、私用中の事故であっても会社の使用者責任や運行供用者責任が認められる傾向にあります。
Q3. 会社が被害者に賠償金を支払った後、事故を起こした従業員に全額請求することはできますか?
全額の請求は制限されることが一般的です。
会社は従業員に対して、支払った賠償金の一部を負担するよう求める権利(求償権)を持っていますが、その範囲は「信義則上相当と認められる限度」に制限されます。具体的には、事故の態様や普段の労働条件、会社の安全管理体制などを考慮し、多くの場合は損害の一部(例えば2割〜数割程度)の請求に留まります。ただし、飲酒運転や故意による事故など、悪質性が高い場合は全額請求が認められる可能性もあります。
解説:会社の「使用者責任」が問われるケースと法的構造
1. 使用者責任とは(民法715条)
使用者責任とは、ある事業のために他人を使用する者(会社)が、その被用者(従業員)が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任のことです(民法715条1項)。
運送会社がこの責任を負わされる根拠として、法的には主に以下の二つの考え方が挙げられます。
- 報償責任の原理: 他人を使用して利益を上げている以上、その活動から生じる損失(損害賠償)も負担すべきであるという考え方。
- 危険責任の原理: 危険を伴う活動(自動車の運行など)を行う主体は、そこから生じるリスクも管理・負担すべきであるという考え方。
運送業はまさに、多数の車両とドライバーを使用して利益を上げ、同時に公道上でのリスクを管理する事業であるため、使用者責任が厳格に適用される業種といえます。
2. 使用者責任の成立要件
会社に使用者責任が成立するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 使用関係が存在すること
正規雇用の従業員だけでなく、アルバイト、パート、派遣社員であっても、実質的な指揮監督関係があれば「使用関係」が認められます。また、元請け・下請けの関係であっても、元請けが下請けの業務を実質的に指揮監督していたとみなされる場合は、元請けに使用者責任が及ぶことがあります。 - 従業員が第三者に損害を与えたこと(不法行為の成立)
従業員自身に過失(前方不注意、スピード違反など)があり、不法行為責任(民法709条)が成立することが前提です。従業員に全く過失がない不可抗力の事故であれば、当然ながら会社も責任を負いません。 - 事業の執行についてなされたこと
事故が業務に関連して発生したものであることが必要です。この「事業の執行について」という要件が、実務上もっとも争点になりやすいポイントです。
3. 「事業の執行」の範囲と判断基準(外形標準説)
「事業の執行について」という言葉は、文字通り「仕事中」だけを指すのではありません。判例では、「外形標準説」という考え方が採用されています。
これは、従業員の行為が実際に会社の命令によるものだったか、あるいは従業員の内心がどうだったかに関わらず、「外形から客観的に観察して、職務の範囲内の行為に見えるかどうか」で判断する基準です。
具体的なケーススタディ
- 休憩中の事故
配送ルートの途中で食事や休憩をとるために運転していた際の事故は、通常、業務の遂行に伴うものとして「事業の執行」に含まれます。 - 通勤中の事故
マイカー通勤の場合、原則として通勤は私的な行為とされますが、会社がその車両を通勤に利用することを積極的に容認・推奨していたり、業務にも使用させていたりする場合は、使用者責任が肯定されることがあります。社有車での通勤であれば、より責任が認められやすくなります。 - 業務からの逸脱(私用運転・寄り道)
業務中に大幅にルートを外れて私用を済ませる際の事故や、業務終了後に無断で社有車を持ち出して起こした事故などは判断が分かれるところです。
しかし、会社のロゴが入ったトラックを使用している場合や、制服を着用している場合など、第三者から見て「業務中」に見える状況であれば、会社に責任があると判断される可能性が高くなります。特に運送業においては、車両管理(鍵の管理など)が会社の義務であるため、管理不十分による無断使用事故については、会社側の責任が重く見られる傾向にあります。
4. 会社が免責される(責任を負わない)ケースとは?
民法715条1項ただし書には、以下のような免責規定があります。
「ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」
条文上は、会社が従業員の選任・監督について「相当の注意」を尽くしていれば、責任を免れることができるとされています。
しかし、実務上、この免責が認められることは「極めて稀」です。事実上、ほぼ認められないと考えて差し支えありません。これを「空文化」といいます。
特に自動車を扱う運送業においては、事故による被害が甚大になることが多いため、裁判所は会社に対して高度な監督義務を課しています。「一般的な安全講習を行っていた」「口頭で注意していた」という程度では、「相当の注意を尽くした」とは認められません。
したがって、経営者としては「免責を主張して戦う」ことよりも、「責任は発生するもの」という前提で、いかに予防するか、あるいは発生後の損害をコントロールするかに注力する必要があります。
5. 自動車損害賠償保障法(自賠法)との関係
交通事故の人身損害(怪我・死亡)については、民法の使用者責任に加えて、自動車損害賠償保障法(自賠法)3条の「運行供用者責任」が適用されます。
- 運行供用者とは: 自動車の運行を支配し、その運行から利益を得ている者のこと。通常、車両の所有者である会社はこれに該当します。
- 立証責任の転換: 自賠法では、会社側が「自分と運転者が注意を怠らなかったこと」「車両に欠陥がなかったこと」「第三者の故意・過失があったこと」の全てを証明しない限り、責任を免れることができません(無過失責任に近い責任)。
つまり、人身事故においては、民法の使用者責任よりもさらに厳しい基準で会社の責任が問われることになります。一方で、物損事故(車やガードレールの破損など)については自賠法の適用がないため、民法の使用者責任の成否が中心的な問題となります。
6. 会社から従業員への求償権(損害賠償請求)
会社が被害者に賠償金を支払った場合、本来過失があったのは従業員ですから、会社は従業員に対してその分を負担するよう請求することができます。これを「求償権(きゅうしょうけん)」といいます(民法715条3項)。
しかし、ここで重要なのが、「会社は従業員に全額を請求できるわけではない」という点です。
茨城石炭商事事件 最高裁昭和51年7月8日第一小法廷判決の基準
過去の最高裁判例では、以下のように述べ、求償できる範囲を制限しています。
「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ、被用者に対し損害の賠償又は求償の請求をすることができる」
考慮される要素
裁判所は、以下のような要素を総合的に判断して、従業員の負担割合(例えば損害額の5%、25%など)を決定します。
- 労働環境: 過労運転を強いていなかったか、タイトすぎる配送スケジュールではなかったか。
- 安全管理: 適切な安全教育、車両の整備、点呼の実施が行われていたか。
- 事故の態様: スピード違反、居眠り、飲酒などの重過失があったか、あるいは単純な不注意か。
- 従業員の地位・給与: 責任に見合った待遇を与えていたか。
一般的に、単なる不注意による事故であれば、従業員への求償は損害額の数割程度に制限されることが多いです。逆に、飲酒運転や無免許運転、会社に無断での私用運転など、悪質性が高い場合は、求償割合が高くなる、あるいは全額求償が認められる可能性もあります。
弁護士に相談するメリット
運送会社における交通事故対応は、初期対応から示談、従業員への対応まで、複雑な法的判断が求められます。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
- 会社の責任範囲の正確な判断
事故の状況を精査し、使用者責任や運行供用者責任が及ぶ範囲を法的に分析します。特に、業務外使用や下請け業者の事故など、判断が微妙なケースにおいて、不当に広範な責任を負わされることを防ぎます。 - 被害者との示談交渉の代行
会社が直接被害者と交渉すると、感情的な対立が生じたり、相場からかけ離れた高額な賠償金を請求されたりするリスクがあります。弁護士が代理人となることで、法的根拠に基づいた適正な賠償額での解決を目指すことができます。 - 従業員への適切な求償と労務対応
事故を起こした従業員に対して、どの程度の求償を行うべきか、また懲戒処分を行う場合に法的に問題がないかなど、労務管理の観点からのアドバイスを提供します。不適切な求償や処分は、後に従業員から訴訟を起こされるリスクとなるため、専門家の判断が不可欠です。 - 予防法務としての体制構築
事故は起きてからの対応だけでなく、起こさないための体制づくりが重要です。雇用契約書や就業規則の見直し、車両管理規程の整備、効果的な安全教育の実施など、法的観点から事故リスクを低減させるためのコンサルティングを行います。
まとめ
運送業において、従業員が起こした交通事故について会社が「使用者責任」を問われることは、法制度上、ほぼ避けられないリスクであると言えます。特に「事業の執行」の範囲は広く解釈され、会社側の免責が認められるハードルは極めて高いのが現実です。
しかし、責任を負うことと、不当な要求に応じることはイコールではありません。
適切な初動対応を行い、法的に適正な賠償額を算定し、従業員との間で公平な責任分担を行うためには、専門的な法的知識が必要です。
また、万が一の事故に備えて、任意保険の限度額を見直すことや、日頃からの労務管理・安全指導を徹底し、それを記録に残しておくことは、裁判になった際に会社の誠実な管理体制を証明する重要な証拠となります。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、運送業界特有の事情に精通した弁護士が、交通事故対応から労務管理、予防法務までトータルでサポートいたします。
「事故を起こした従業員への対応に困っている」「被害者からの請求額が妥当か知りたい」など、少しでも不安な点がございましたら、お早めにご相談ください。企業の護り手として、最善の解決策をご提案いたします。
【弁護士法人長瀬総合法律事務所のYouTubeチャンネル 】
企業法務に関する問題を解説したYoutubeチャンネルを運営しています。
ぜひご視聴・ご登録ください。
【メールマガジンのご案内】
無料WEBセミナー開催のお知らせや、事務所からのお知らせをメールで配信しています。
ぜひこちらのご登録もご検討ください。